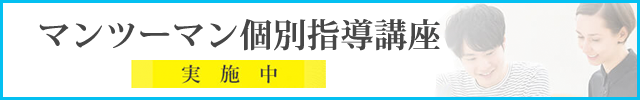埼玉県・神奈川県で公務員になるには?
この記事の目次
~民間企業などでの社会人経験を活かした採用試験について~
社会人経験がある方でも受験できる公務員試験には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、埼玉県と神奈川県で秋に実施される、行政職の採用試験についてご紹介します。
1.「埼玉県庁で働く」ということ
全国で最も「市」の数が多い都道府県をご存じでしょうか?
実は、埼玉県は40市を有し、全国最多です。
県庁で働くということは、多くの市町村や国、民間企業との調整を担う「広域行政」に携わることを意味します。関係機関が多いほど、連携や調整の機会も増え、非常にやりがいのある業務です。
埼玉県庁では以下のような部署に職員が配置されます。
- 知事部局(企画財政部、総務部、県民生活部など)
- 教育局
- 企業局
- 県税事務所 など
※一般行政職の場合、警察本部以外のすべての部局が異動対象となります。
経験者採用で入庁された場合は、まず「主事(技師)」または「主任」としてのスタートになります。
その後のキャリアアップに関しては、基本的には次のように昇任が行われます。
主事(技師)・主任 → 主査級(昇任試験・選考) → 主幹級 → 副課長級 → 課長級 → 副部長級 → 部長級
2.埼玉県庁の民間企業等経験者採用試験
埼玉県庁では、春と秋の年2回、民間企業などの職務経験者を対象とした採用試験を実施しています(同一職種での両方の試験への応募は不可)。
令和7年度・秋実施予定の職種(10種)
- 一般行政、一般行政(DX)
- 福祉、心理
- 設備、総合土木、建築
- 農業、林業、司書
試験日程(秋)
| 内容 | 日程 |
|---|---|
| 受験申込期間 | 8月15日(金)~8月28日(木) |
| 第1次試験 | 9月28日(日) |
| 第1次合格発表 | 10月21日(火) |
| 第2次試験 | 11月1日(土)~16日(日)※土日祝のうち1日 |
| 最終合格発表 | 11月26日(水) |
一般行政職の業務内容
県計画の策定、政策立案、渉外・折衝など幅広い行政事務を担当します。
特定分野の職務経験は問いませんが、民間で培った経営感覚、多角的視点、コスト意識などが期待されます。
試験内容
- 第1次試験:
教養試験(75分/多肢選択式)
論文試験(75分/900〜1,100字程度) - 第2次試験:
人物試験(2回)
※社会性・積極性・信頼性・達成力等を評価
倍率は令和6年度実績で約9倍です。
対策のポイント
- 教養試験の傾向: 社会や判断推理などの基本的な問題など
💡社会科学・人文科学・判断推理・数的処理などを地方上級レベルの問題集や参考書で学習 - 論文試験の傾向: 少子高齢社会において地域活動の担い手不足に関するテーマなど
💡社会課題への関心と、論理的な記述練習が重要 - 人物試験: 模擬面接などで自己PRと志望動機を明確に
3.神奈川県庁・秋季Ⅰ種試験(行政職・大卒程度)
神奈川県では、SPI方式による秋季Ⅰ種試験が実施されます。
公務員試験対策が難しい社会人にも比較的受けやすい形式です。
試験日程・概要
| 内容 | 日程 |
|---|---|
| 申込期間 | 8月29日(金)~9月12日(金) |
| 自己PR動画 | 9月9日(火)~24日(水) |
| 基礎能力検査(SPI3)・性格検査 | 9月25日(木)~10月20日(月)の指定される3週間程度 |
| 論文試験 | 10月31日(金)~11月10日(月) |
| 人物試験 | 11月21日(金)~12月10日(水)(個別面接+プレゼン+グループワーク) |
令和6年度の倍率は約8.1倍(夏季試験は2.8倍)です。
過去の出題例(グループワーク)
歩きスマホの防止対策について条例も含めて話し合う
💡日頃から社会課題に目を向け、自治体としての取組みを考えておきましょう。
中途採用試験(参考)
神奈川県では、31歳~61歳を対象とした行政職・経験者採用も実施中です。
令和7年度の申込締切:7月11日(金)
4.まとめ:試験対策に向けて
| 埼玉県庁(経験者採用) | 神奈川県庁(秋季Ⅰ種) | |
|---|---|---|
| 試験方式 | 教養試験+論文+面接 | SPI3+論文+面接+グループワーク |
| 募集対象 | 経験者(5年以上) | 大卒程度(+別途経験者採用あり) |
| 倍率 | 約9倍 | 約8.1倍 |
いずれも文章理解・判断推理・数的処理が重視されます。
また、論文・面接・プレゼンテーションでは自分の考えを分かりやすく伝える力が求められます。
各試験の特徴を理解し、早めの対策を進めていきましょう。
❗補足:面接・論文・プレゼン対策はこちらも参考に
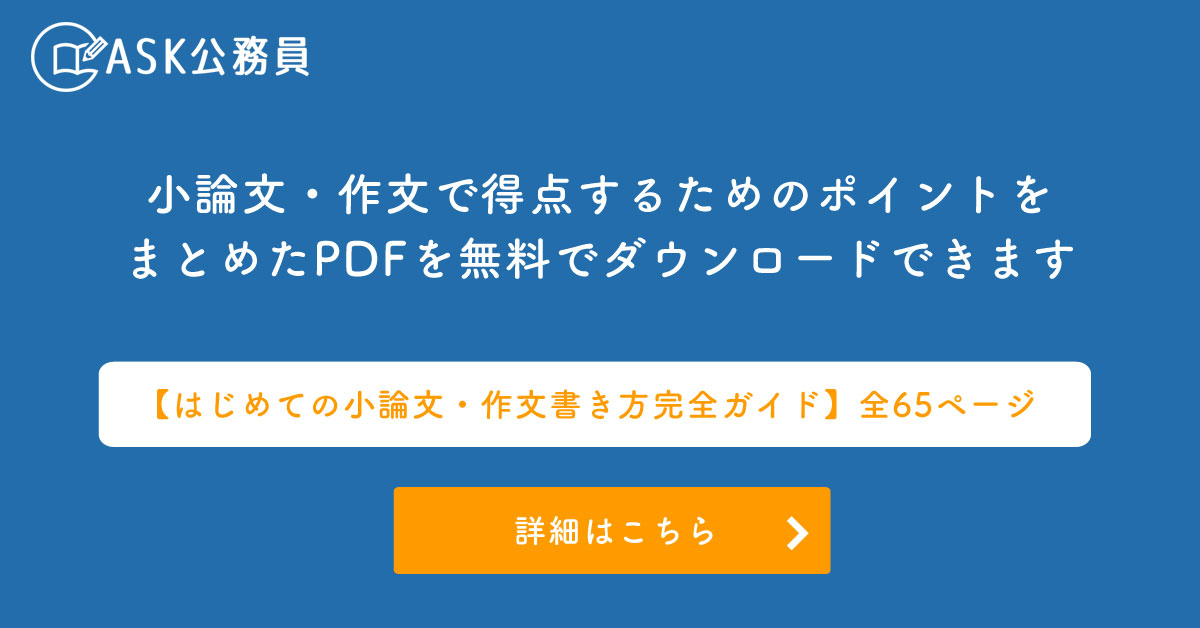

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ