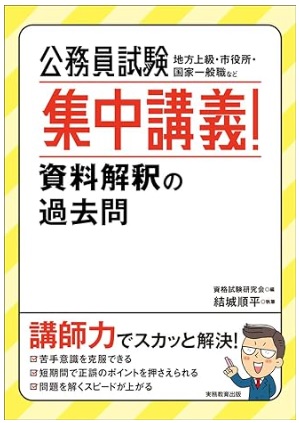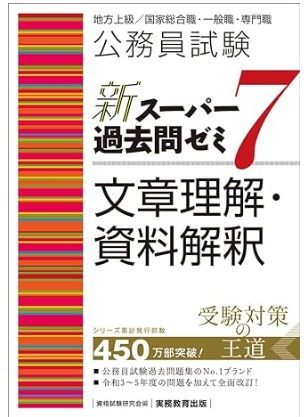資料解釈は勉強のしにくい科目であるがゆえ、解き方やコツについてよくわからず何となく学習を進めている受験生が多いのではないでしょうか。
資料解釈は、教養(基礎能力)試験の知能ジャンルである数的処理に属する科目ですが、受験生にとってどうしても注目が行くのは、「数的推理」や「判断推理」であり、「資料解釈」という科目の性質や対策については、ヴェールに包まれているのが実感でしょう。
また、出題数が数的処理全般からみると多くないので、軽視されている点も否めません。
しかし、ケースによっては(特に数的処理全般が苦手な人にとっては)、「資料解釈」が合否を分けるいわば「キャスティングボート」の存在になるのです。
この記事では、資料解釈の出題数や取り組み方、具体的問題な解き方までお伝えします。数的推理や判断推理が苦手だけど、数的推理全体での得点を何とか高めたい人を中心に参考にしていただければ幸いです。
この記事の目次
1 各試験種の資料解釈の出題数
| 国家公務員総合職 | 16問中2問 |
| 国家公務員一般職 | 16問中3問 |
| 国家公務員専門職(国税・財務・労基・法務省専門職) | 16問中3問 |
| 裁判所大卒一般 | 17問中1問 |
| 外務省専門職員 | 16問中3問 |
| 東京都一類B | 16問中4問 |
| 東京都一類B新方式 | 20問中4問 |
| 地方上級(概ね) | 12~15問中1~2問 |
| 市役所一般(概ね) | 12~14問中1問 |
| 特別区 | 19問中4問 |
これをみると、国家系と東京都、そして特別区で複数問の出題がされている一方で、その他の地方公務員と裁判所一般職では1問ということが分かります。このように、差はありますが、資料解釈はどの試験種を受験する方にとっても取り組むことが望ましい科目です。
というのは、判断推理や数的推理を解く上で必要なのは決して数学ではなく「受験算数」ですから数学アレルギーでも大丈夫と言われる一方で、中学受験未経験者にとってはマスターには一定の時間がかかる上、いくら定石を身につけても太刀打ちできない問題が必ず出てくるからです。
これに対して、資料解釈は、正しく課題文を読み、計算の工夫などのテクニックさえ身につけてしまえば解けます。数的推理や判断推理が苦手な方には得点源となります。それ以外の方にとっても、正解をしやすい科目は大きな魅力でしょう。
2 資料解釈の性質
資料解釈とはどのような科目なのかをつかんでいただくために、次の事例を考えてみて下さい。
ある年のパシフィックリーグの8月終了時点でファイターズとマリーンズが首位争いを演じていた。成績はファイターズが67勝48敗、マリーンズが68勝49敗だった。8月終了時点の首位はどちらか。なお、勝率が上回っているチームが上位となる。
これは試験問題ではありませんが、資料解釈の本質の1つである「スピード事務処理能力」を理解するために分かりやすい例かと思います。
もちろん、67÷(67+48)と68÷(68+49)をそれぞれ計算して勝率を比較すれば答えは出せますが、資料解釈で求めていることはこれではありません。その計算をしっかりやらなくても、どちらが首位かを見抜くことです。
解きなれると、正解がファイターズとすぐに分かり、受験生の方にはそれを目指して欲しいのです(このやり方は、後述します)。
つまり、資料解釈は、まともに計算していたら試験時間を大いにロスしてしまいますので、なるべく計算をせずに正解を求める必要がある科目といえます。その他に、学習を進める上で知っておいていただきたいことが2点あります。
2−1 1問の解答時間が長くなるが問題の質そのものは難しくない
さきほど、計算をしっかりやらなくてもとは述べましたが、法律科目等のように肢を読めば即正誤判断できるわけではありません。必ず「ある程度の」計算処理で検証する必要があります。このため、資料解釈1問を解くのに時間がかかるのは否めません。
とはいえ、先ほどの計算だって根性でやりきれば、すなわち、時間さえあれば、ほとんどの人が解答できます。これは、判断推理や数的推理における問題の解法がわからず歯が立たない事態とは大きく異なります。資料解釈は確実に遠回りすれば正解に至れるものの、なるべく早く問題を処理できるといいよねという科目なのです。
2-2 テクニックを自力で習得しにくく慣れるまで時間がかかる
繰り返しますが、1問の解答時間が他の科目より長くなりがちです。そして、まともに計算していては教養試験全体を通じて、他の科目を解答する時間が激減してしまいます。これでは、教養試験の得点が満足なものにならない事態を引き起こす蓋然性が高まります。
そのため、計算の工夫などテクニックの習得が肝要となるわけです。ただ、これを知って、自分のものにするとなると、大変です。
予備校などで指導を受けるか、参考書を読むかすれば、このテクニック自体を知ることはできます。他方、使いこなすまでには練習が必要です。特に、様々な異なったデータに出くわすので、瞬時に表やグラフの見方をつかみ、肢ごとにデータを見ながらの作業になるので、かなりの慣れが必要となるでしょう。
ただ、一度テクニックを身につければ(要するにコツを飲みこめば)、一気に得点力やスピードは上がってきます。その意味で、前述の通り、数的推理や判断推理と違い努力が報われやすい科目と言えます。
3 資料解釈の対策
3−1 学習開始タイミングについて
予備校に通っている人であれば、そのスケジュールに合わせれば良いでしょう。注意点としては数的推理や判断推理に比べて、資料解釈の授業の回数は極めて少ない傾向にあります。
このため、必要な問題量やテクニックの習得を予備校の期間だけで知るのは難しく、授業で触れられていない箇所もテキストを読み込む必要があります。もちろん、問題演習をさらに行うわけなので、地道な家庭学習で積み上げる必要があります。
独学の方は、少なくとも数的推理は習い終えてからにして下さい。「まともに計算はしない」とはいえ、算数の熟練をしておく必要があるからです。判断推理については必ずしも終了していなくてもかまいません。
3−2 資料解釈はブランクを空けてはいけない
資料解釈に関しては「練習は裏切らない」科目といえます。ただ、「サボればすぐに力は落ちる」科目でもあります。まるで、筋トレ科目です。
大学生の場合ですと、12月に大学の試験があるので、終わってからだと1月スタートになり遅くなると考え、11月に一通り習得して1月に再開しよう(12月は休むという意味)とした人がいます。
しかし、1ヶ月ものブランクがあると、11月に時間をかけてやっとことがほぼムダになります。資料解釈は、学習を開始したらできれば毎日(空けても3日ほど)やるべきです。この場合、11月は別の科目に力を入れ、1月スタートしたほうが効率的となります。
3-3 資料解釈の学習について
資料解釈を学習する上で以下の2点を守っていただくことでかなり力がつくようになります。
①過去問1問単位ではなく、肢別に正誤とその理由が言えるまで練習しましょう。
正解が3と判っても、4はなぜ違うのかを根拠となるテクニックが言えるまで習得します。
②使ったテクニックを自分のものとするために、資料解釈ノートを作り、過去問の肢ごとに正誤とその理由、使ったテクニックを記入していきましょう。過去問1回目は時間がかかりますが、かなり力がつきます。
以上を今後の参考にしてみて下さい。
4 資料解釈の解き方
ここでテクニックのすべてを述べることはできませんが、テクニックのイメージをつかんでもらうために「打率理論」を述べてみます。次の事例で理解して下さい。
あるバッターは前日まで10打数2安打で打率2割
本日は2打数1安打の成績だった
打率は上がったか下がったか
この程度の問いなら成績を合算して本日終了時点でで通算12打数3安打だから打率は2割5分(3÷12=0.25)と計算しても時間はかかりません。
問題は瞬時に見抜く方法です。
本日だけの打率を考えると2打数1安打ですから打率5割(1÷2=0.5)となります。
つまり、前日までこのバッターは2割のペースでヒットを打ってきて、本日5割と今までよりハイペースで打ったわけです。すると通算のペースは必ず上がることになります。
打率をテストの平均点に置き換えるとよくわかるでしょう。今まで受けたテストの平均点が20点だった人が、本日50点取ったわけです。テストの平均点が上がったか下がったか計算する必要がありますか。
このケースを例にとると「打率はいくらになったか」とは一切聞いていません。
ただ「打率は上がったか下がったか」と聞いているだけです。
これが資料解釈なのです。数的推理なら正確な打率を求めなければならないでしょう。
「大局観掌握能力」により、瞬時に(実際の試験なら簡単なメモ程度で)アウトラインをつかむことが必要となります。
では、前述したパシフィックリーグの首位争いの事例を説明してみましょう。
ある年のパシフィックリーグの8月終了時点でファイターズとマリーンズが首位争いを演じていた。成績はファイターズが67勝48敗、マリーンズが68勝49敗だった。8月終了時点の首位はどちらか。なお、勝率が上回っているチームが上位となる。
勝率はどちらが高いかですね。勝ち越しの数は共に19でいわゆるゲーム差なしの状態です。
仮にファイターズだけが今2試合戦って1勝1敗なら、マリーンズと全く同一になります。ところで1勝1敗は勝率5割のペースです。ファイターズの今までの成績は勝ち越しているわけだから当然勝率は5割を超えています。
ファイターズが今までより悪いペース(5割)で戦えば、勝率は当然下がります。その下がった勝率が現在のマリーンズの勝率なのですから、現在はファイターズの方が勝率が上ということです。
お分かりの通り、何の計算もしておりません。それで答えを出せるのです。
最後に実際の過去問(国家専門職)の問題の一部抜粋から「打率理論」を使ってみます。
問:国民総支出に占める民間最終消費支出の構成比は、昭和62年度から平成2年度まで毎年上昇している。正しいか否か。
昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 国民総支出 (単位:兆円) 350 370 388 408 民間最終消費支出(単位:兆円) 206 217 225 233
206÷350、217÷370、225÷388、233÷408を全て計算して比較することは時間の無駄であることはもうお分りかと思います。
<解法>まず「毎年上昇」とあるから1か所でも下降していれば間違っている部分が明らかとなります。
「打率理論」で考えると、国民総支出と民間最終消費支出の各年度の増加数は以下のように考えることができます。
各年度はすべて打率5割を超えている。
S63~H元:(388-370=18、225-217=8)→18打数 8安打
H元~H2:(408-388=20、233-225=8)→20打数 8安打
18打数8安打と20打数8安打は打率5割未満であり、前年度までが5割超の打率なので、悪いペースとなり明らかに下降しているのが分ります。したがって、この問いは×となります。
このように簡単な計算をするだけで資料解釈は正解を導くことができるのです。
ただし、前述のようにテクニックを身につけるには時間がかかりことや量をこなさなければいけないことが条件となるため、得点できる科目ではありますが、決して「簡単に」得点できるものではないということを知っておいてください。
5 資料解釈のおススメ参考書
資料解釈は、テクニックを学ぶ参考書と練習ができるもの(演習本)を併用することがおススメです。もちろん、予備校に通っている方は、テキストと問題集があるので、それに励めば大丈夫です。以下では、独学の方にその2種類に分けておススメの参考書を紹介します。
5-1 テクニックを学べる本
テクニックが学べる本としては、次の2冊のいずれかです。
① 実務教育出版『公務員試験 集中講義! 資料解釈の過去問』
この本は、計算方法を分かりやすく説明したページが付録としてあり、解法がジャンルごとにまとめられています。また、問題ページと解説ページが分かれているのでレイアウト的にもみやすくなっています。
国家総合職などの難関公務員を目指す方には物足りないかもしれませんが、国家一般職・専門職、地方上級、特別区、市町村などが第一志望ならば問題ない水準です。
これで土台を固めて演習に入れば資料解釈の得点源化は達成するでしょう。
②畑中敦子の資料解釈の最前線
大手予備校のLECさんと、数的処理科目の出版女王の畑中氏がタッグを組んだ本です。令和版となって、近年の問題の収録もなされています。
同書は、テクニック集が付録となっており、早く解くための工夫が問題を通じて分かりやすく解説してくれています。レイアウトが見にくいところが難点ですが、すいすい読んでいく形で解法テクニックを理解する意味では有意義な本です。
①と②は本屋などで実物を眺めて決めていけば良いでしょう。
5-2 演習本のおススメ
演習に取り掛かる時に大事なのは、解説の丁寧さもさることながら、収録している問題数です。なぜなら、毎日のように解くことを勉強法として推奨しているからです。
例えば、受験年1月に資料解釈のテクニックを知識として注入したとして、2月から5月くらいまでの4か月(=120日ほど)が国家系や地方上級を受ける場合の日数です。この辺りを志望している受験生は、この期間内、毎日のように行えるボリュームの本を選んだ方が良いことになります。
この観点でいくと、実務教育出版の『スーパー過去問 文章理解・資料解釈』がおススメとなります。同書は120問が収録されています。解説はやや硬いですが、上記のテクニックを注入する本を経由しているので大丈夫かと思います。他の本に手を出す場合、必ずどのくらいの問題数があるかを確認してください。
6 まとめ
資料解釈は数的処理が苦手な人は必ず得点して欲しい科目です。
あまり対策をせずに試験に挑む人やましてや捨てる人を多く見かけます。ただ、これはとても勿体ないことです。
ここで紹介した資料解釈への取り組み方を参考に、得点できるよう練習を繰り返してみてください。応援しています。
おすすめの記事
数的処理対策講座のご案内

・これから公務員試験の勉強を始めるけれど数的処理は早めに対策したい方
・数的処理や数学がとにかく苦手な方
・これまで予備校や学内講座を受講しているけれど一向に解けるようにならない方
・独学で勉強しているが数的はどうしても分からない方
数的処理は早めに対策を行うことが重要です。このような方はぜひご相談ください。
個別指導によりあなたに合ったプランを作成し合格のサポートをいたします。
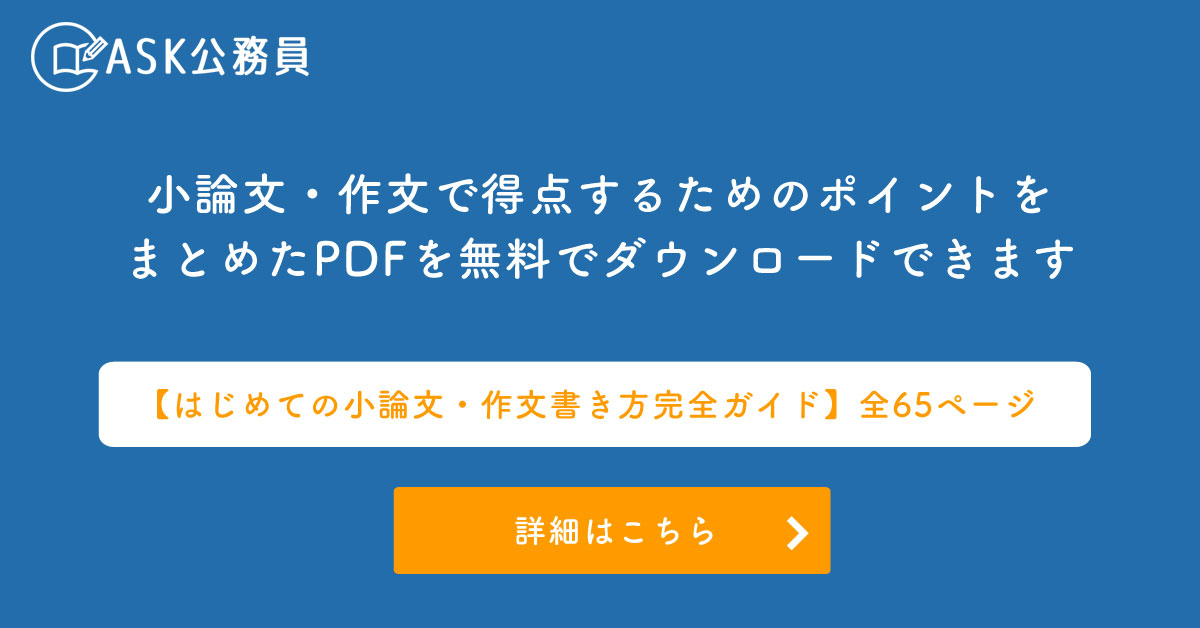

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ