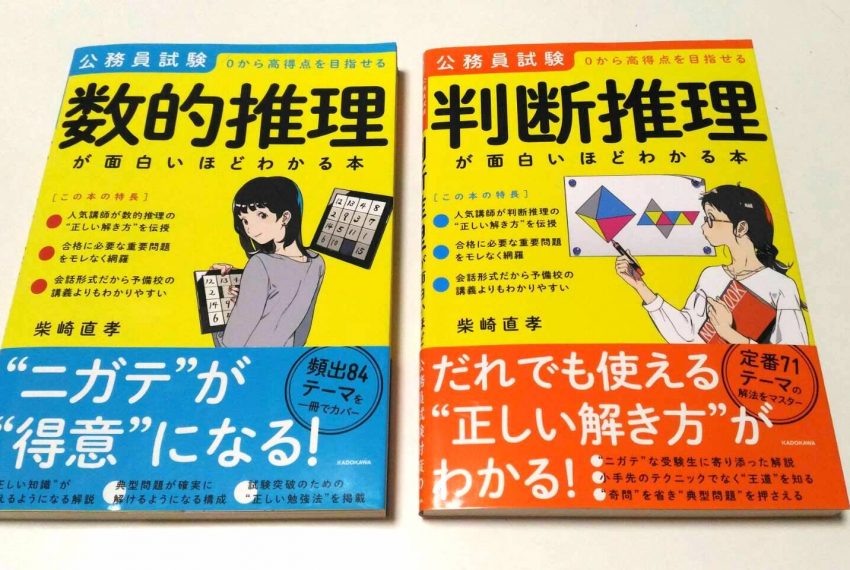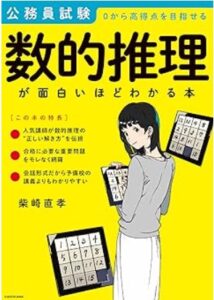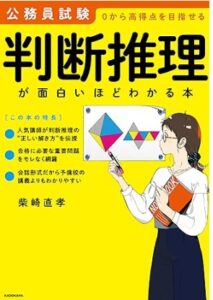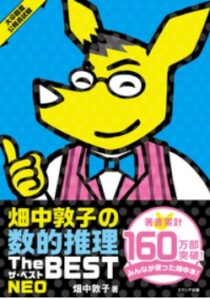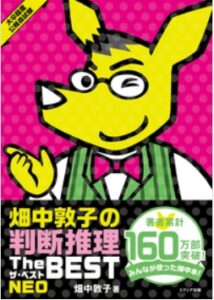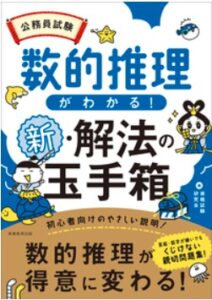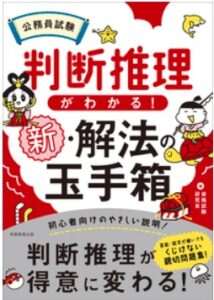1.はじめに
2018年にKADOKAWAから出版された、柴崎直孝「数的推理が面白いほどわかる本」「判断推理が面白いほどわかる本」を紹介します。
公務員試験における数的処理は、合否を左右する重要な科目です。
そのため過去問をとにかく解くことは欠かせません。ただ、数的処理を苦手としている人の場合、いきなり過去問に向かっても挫折する可能性が高いです。このとき、予備校や市販のテキストを併用することが一般的です。
そして、市販テキストで有名なものといえば、畑中敦子氏の「畑中敦子のゼ・ベスト」シリーズ(令和6年時点でNEOが最新版)であり、予備校を使わない独学組に愛用されています。
一方、大手予備校講師として畑中敦子講師に匹敵するほどの人気講師だった柴崎直孝講師が書いた「数的推理(判断推理)が面白いほどわかる本」も使っている方がいる、ロングセラー商品といえます。
「面白いほどわかる本シリーズ」自体、大学受験の参考書としても多く出版されているシリーズであり、こうしたシリーズのラインナップをされること自体、信頼性の高い本だと感じます。
今回は、この「数的推理(判断推理)が面白いほどわかる本」が本当に面白いほどわかる本なのか、他のテキスト関係の本との比較などもしながら検証してみたいと思います。
2.全体のレビュー
本書は、「数的推理が面白いほどわかる本」と「判断推理が面白いほどわかる本」の2分冊になっています。
各項目(分野)について見開き2〜3ページ程度にまとまっており、黒・赤の2色刷りのためにとても読みやすいです(テキストによっては色を多用して、かえって読みづらいものもあるので)。
また、各項目(分野)ごとに、
| ①重要度(ABC) ②到達目標(「〇〇できるようになる」という表記がある) ③問題と解説 ④出典(どの試験で出題されたか) ⑤難易度(5段階) が書かれています。 |
このうち、①重要度と⑤難易度は、受験生にとって学習の指針になります。著書は長年にわたり公務員試験の数的処理を研究してきた講師なので信頼がおけます。とはいえ、2024年時点で6年ほど著書出版から経過していますので、公務員試験ジャーナルなどを読んで、最新傾向を補う必要があります。
全体のボリュームは薄いです。例えば、上述の畑中敦子著、それから公務員試験対策本で定評ある実務教育出版から出ている「玉手箱」シリーズと比較すると、以下となります。
| 柴崎氏の面白いほど分かる本 | 畑中氏のザ・ベストシリーズ | 実務教育出版の玉手箱シリーズ | |
| 数的推理 | 240ページ | 384ページ | 315ページ |
| 判断推理 | 240ページ | 400ページ | 326ぺージ |
こうして比べると、「面白いほどわかる本」の薄さが分かると思います。ただ、著者も述べていますが、本書は「問題集というより、参考書」です。
「ザ・ベストシリーズ」が、単元を貫く知識の伝授という知識面だけでなく、問題集として各単元にまつわる様々な問題を収録している「テキストと問題集一体本」であるのに対し、「面白いほど分かる本」は単元にまつわる考え方に特化した本であるといえます。
なお、「玉手箱シリーズ」は、特に数的等では、算数・数学のおさらいなどがあり、苦手層にフォーカスしたテキスト本の体裁となっています。
これに比べると、「面白いほどわかる本」は、そこまで苦手層にフォーカスしている感じとは言い難いです。とはいえ、受験生と講師(多分、柴崎講師と思われるイラスト)の対話形式で解説が進むので、難解な印象はありません。
なお、Amazonの口コミレビューにもありますが、ASK編集部としてもハマったポイントは、ところどころに挿入されている「コラム」です。ここに、大手予備校で人気講師だった著書からの熱いメッセージや、ちょっとしたプライベートが垣間見られ、学習に良いアクセントが生まれています。
もちろん、どれも受験に役立つ内容になっています。しかも、コラムの数がけっこうあるので、次のコラムを楽しみに読み進めることができます。
3.数的推理のレビュー
全16章84項目を扱っており、頻出単元で扱われていないというところはないといえます。そして、「場合の数」「図形の計量」「速さ」という数的推理3大出題は、これを踏まえかなりの項目数を割いて典型出題に基づく必要知識を述べています。
ただ、上述のページ数と会話調という影響を受けていますので全84項目共に、1項目につき1問です。本来は、単元の知識を吸収後、その知識に基づいて何題か解きたいところですが、そのような構成にはなっていません。
加えて、数的推理に必要な数学力について、「分数の四則演算」「方程式の途中計算」「平方根」「図形の面積」などが数的処理を解きながら覚えないけれど「知っておいて欲しい」との言及をしつつ、その数学的知識を解説するページを特別に設けているわけではありません。算数や数学の基礎に大きな不安のある人は、別書などで補う部分が必要といえます。
とはいえ、その知識伝授については、圧倒的な分かりやすさを誇ります。また、会話調の部分だけでなく、問題を解くのに必要十分な図を与えてくれますので、視覚的な理解促進もなされています。さくさくとスピーディーに知識を得ることには向いています。
また、冒頭の2項目は、数的推理という科目の特徴である「推理」の大切さを教えてくれます。上述したコラムと合わせると、どのように数的推理を学習していけば良いかが見通せる本になっているといえるでしょう。
4.判断推理のレビュー
全20章71項目を扱っており、数的推理と同様に、頻出単元に重きをおいて、その他の単元も含めて過不足なく扱っています。そして、判断推理も、単元知識を吸収後に、その知識に基づいて何題か解ける訳ではないところも同様となります。
判断推理では、表や図を自分で書いて解く必要がありますが、どのようなものを書けばよいのかを前半の単元で、しっかりと示してくれています。
そのため、苦手な人はもちろん、特に得意というわけでなければ、本書をただ目で見て読むだけではなく、実際に手を動かして、表や図をそっくりそのままマネして書いてみると効果的になるかと思います。
後半の単元は、図形についてたくさんの問題・解説ですが、ここはコンパクトで会話調という本書の特徴が少し課題に感じる要素になってしまっているかもしれません。
例えば「ザ・ベストシリーズ」ですと、図を多く掲載しています。これに対し、一つの図で複数を本書では説明していますので、図形問題を苦手としている人には読みづらいかもしれません。
とはいえ、予備校で講義を聞くとなると、理解が追いつかないときでも次へと進んでしまいますが、本だとじっくり向き合えるため、大きなデメリットとはならないでしょう。
5.まとめ~「面白いほどわかる本」がお勧めな方~
『面白いほどわかる本」は、著者が述べているように「参考書」です。この意味を十分理解して使用するのであれば、効果の大きい本といえます。
具体的には、必ずこの本だけで対策を終わらせないことです。この本で知識を得たら、市販の問題集で演習をする必要があるということです。
これを踏まえると、「面白いほどわかる本」をお勧めする人は以下となります。
| ・数的処理に関して、知識を得る本と問題演習の本を分けたい人で、知識をスピーディーに得たい人 ・数的処理の学習方法や公務員試験の突破に関する心構えなどを得たい人 ・計算の仕方や図形の公式など、算数や数学の基礎と思われる部分への不安が少ない人 |
一方、テキストと問題集を一体的に使いたかったり、図形問題で丁寧に図を何個も使って説明してもらいたい方には、「ザ・ベストシリーズ」がお勧めとなります。また、算数や数学の基礎を補ってもらってから数的処理の学習をしたい場合は「玉手箱シリーズ」がお勧めです。
レビューを参考に、ご自身に合った参考書で合格を掴み取ってください。応援しています。
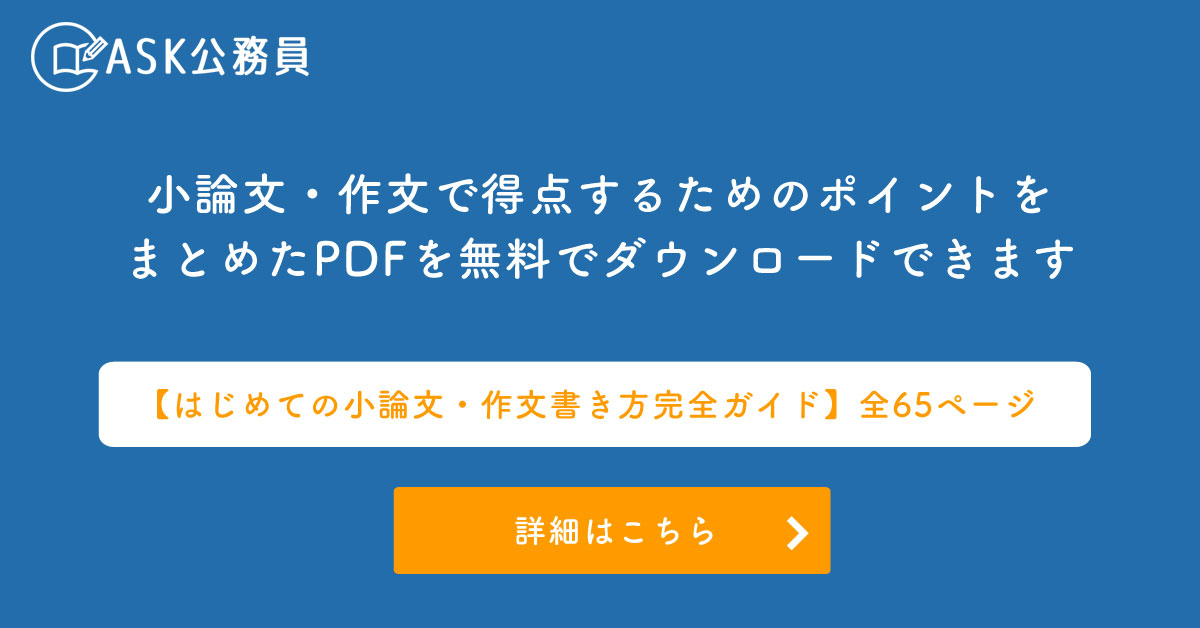

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ