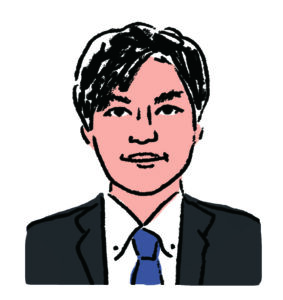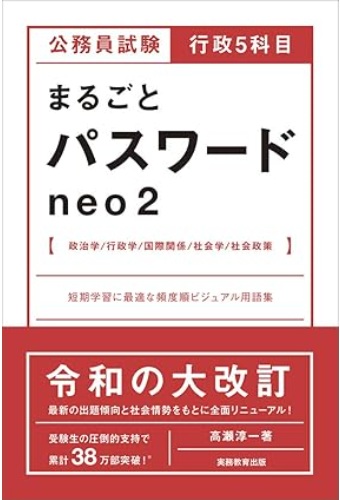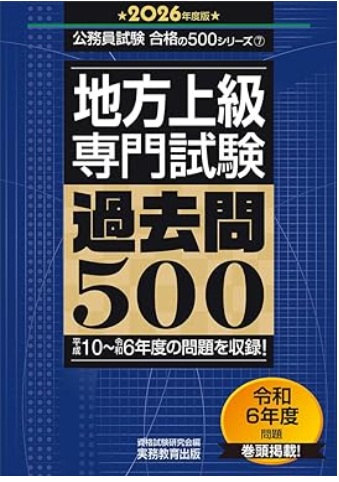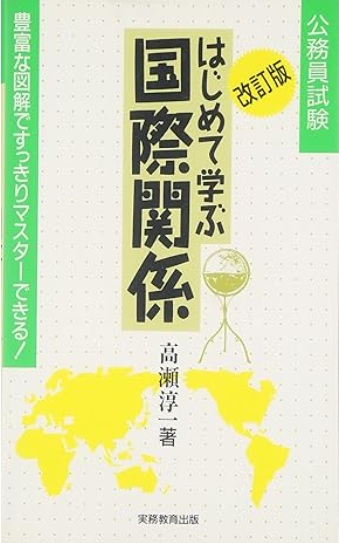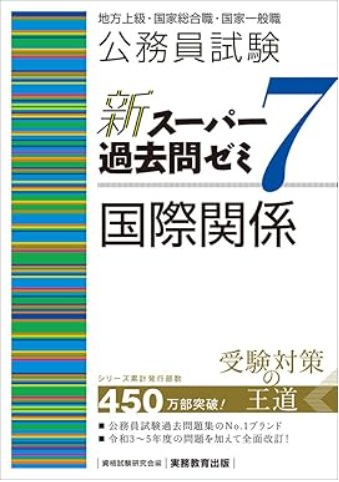1.はじめに
公務員試験で専門科目がある方の多くは、【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】を学習することで、国家一般職・国家専門職(例えば国税専門官)などに備えようとします。
そして、地方上級(都道府県庁や政令指定都市の市役所)も加えて受験しようとしたとき、上記の科目だけだと、「労働法・刑法・社会政策・国際関係」も必要なのか……となります。
「上記の【】だけでも大変なのに、加えて数的をはじめとした教養試験だって大変なのに、この4科目まであるなんて! 手が回らないよ」と焦ってくる方も多いと思います。
本記事では、行政系である「社会政策」と「国際関係」に絞って、出題数、そもそも対策をすべきなのか、するなら、どのように対策をすると良いのかを解説します。「刑法・労働法」は下記の記事をご確認ください。
ご一読いただき、参考になれば幸いです。
2.社会政策と国際関係の出題数
社会政策と国際関係の出題数を確認しましょう。
社会政策は、基本的には地方上級でしか出ないと捉えれば良いでしょう。全国型が必須3問(40問)、中部北陸型が選択2問(40問)、関東型が選択で3問(40問)です。
※( )内が総回答数です。以下、本記事内同じ
国際関係は、国家一般職で選択することが可能です。また、地方上級は、全国型が必須2問(40問)、中部北陸型が選択2問(40問)と関東型が選択で3問(40問)です。
3.社会政策と国際関係は選択すべきか
出題数のあり方から、地方上級が本命でなければ、両科目とも選択を考えなくて良いでしょう。【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】をしっかりやり込むことに専心してください。
次に、地方上級が本命の方ですが、中部北陸型・関東型の方は選択ですから選ばないことができます。なぜなら、【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】だけで、経済学、財政学を通じて経済政策や経済事情も回答する場合、40問の回答数に至るからです。
また、地方上級の全国型は必須とはいえ、社会政策と国際関係を合わせて5問です。40問中28問(7割)を正解するように学習していく際に、基幹となる【憲法・民法・行政法・経済原論(ミクロ・マクロ)・財政学・政治学・行政学・社会学・経営学】をしっかり学習し、刑法や労働法を捨てないのであれば、捨てても良いかもしれません。
ただ、刑法は、以下の記事で紹介したように、本来難関と言われる学習内容です。そのため、法学部生以外はとっつきにくいかもしれません(いきなりスーパー過去問での学習はしづらいわけです)。
他方、労働法はそこまでの難易度ではありません。いきなりスーパー過去問での学習が可能です。また、労働法の法改正点などは時事的な内容です。そして、時事は教養試験対策で必ず学習した方が良いものとなります。
加えて、社会政策も労働政策や社会保障など政策的な事柄における時事的なものが出ます。つまり、労働法と社会政策は似た学習項目があります。したがって、社会政策は学習をしておくと良いでしょう。
そして、国際関係は教養世界史をベースに、国際関係に関する理論や時事が問われます。時事も教養対策で学習するかと思いますので、専門科目用におさえる部分は理論だけとなります。この意味で、国際関係に手を伸ばすことは悪くない選択といえます。
ただ、国際関係などは世界史なども絡むこと、学者と理論を覚えるのは政治学や行政学、社会学で手一杯だという方は苦しいかもしれません。まだ、労働法の方が馴染みがあるかもしれません。
したがって、地方上級は全国型で必須の方は、社会政策は学習しておき、国際関係か労働法のうち相性の良い方を最低でも1つは行いましょう。そうすれば、40問中35問は学習した科目を学習している状態がつくれます。頑張って刑法以外3科目を行えば、40問中38問です。そのつもりで準備しましょう。
4.選択した場合の学習方法
社会政策と国際関係の学習方法について、以下がお勧めとなります。
(1)社会政策の学習
社会政策は、労働政策や社会保障政策の時事的な内容も問われるため、必ず最新版を手にしましょう。と言いたいところなのですが、2025年2月現在、社会政策のテキストはTAC版2018年、まるごとパスワード2019年となっていますので、どちらも心許ないです。
したがって、社会政策の理論部分だけを参考にしましょう。この場合、まるごとパスワードの方がキーワードごとになっていて見やすいので良いと思います。
一読後は、地方上級用の過去問500を使って演習をしましょう(社会政策は、スーパー過去問もないからです)。
演習と合わせて、教養試験対策の時事本で労働事情、社会保障の項目を読みましょう。
まとめますと、社会政策は、①まるごとパスワードでキーワードを読み→②過去問500で演習→③時事本で最新の社会保障政策・労働政策をおさえるという学習の流れがお勧めです。
(2)国際関係の学習
国際関係の学習は、前提として教養の世界史学習を終えておきましょう。
その上で、まず、『はじめて学ぶ 国際関係(改訂版)』でさらっと流れをおさえます。次に、スーパー過去問7で演習をします。その後、教養試験対策の時事本にある国際情勢の項目を読み込みます。
5.おわりに
今回は、公務員試験の専門科目で、多くの職種で問われるわけではない社会政策と国際関係について、選択すべきか、選択する場合はどのような学習が良いのかについて解説しました。
地方上級全国型が本命の方は、社会政策>国際関係≒労働法>刑法の順で学習選択をすることがお勧めだと伝えました。
そして、学習方法は、社会政策が「まるパス→過去問500→時事本」で、国際関係は「はじめて学ぶシリーズ→スー過去→時事本」を推奨しました。
いずれの科目も試験直前に学習することが多いと思います。スピーディーに行いましょう。皆さんの学習が進むことをお祈りしています。
何か悩みがあれば、ぜひ究進塾で受講相談ください。無料体験授業を通じて、少しでも悩みの解消法をお伝えします。
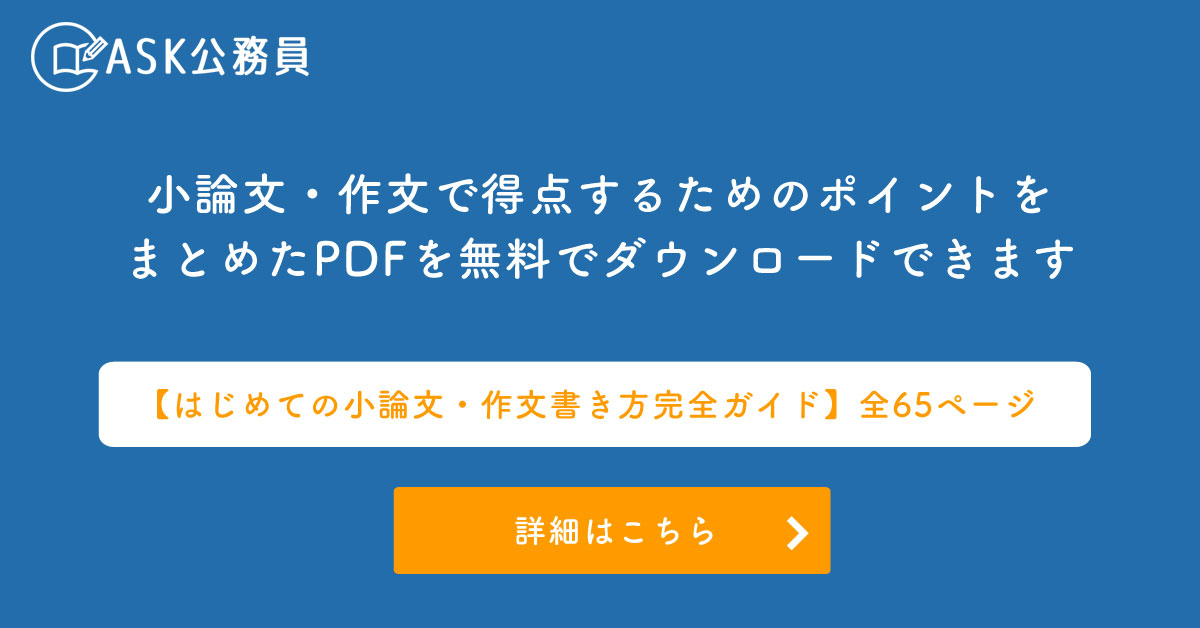

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ