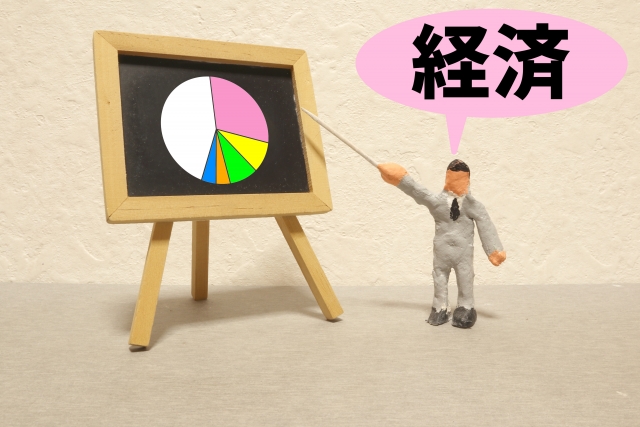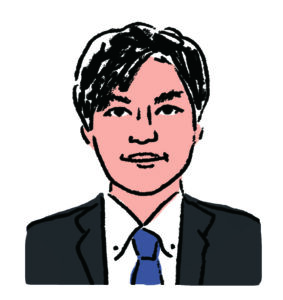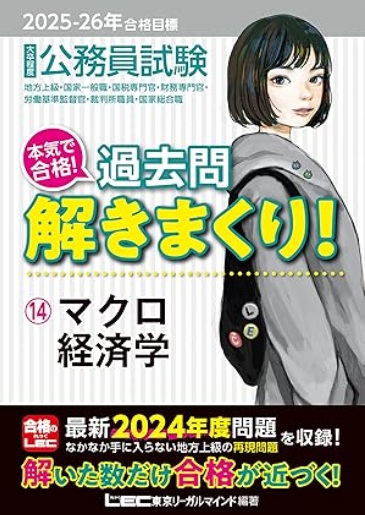1.はじめに
公務員試験において、経済学は、民法と並ぶ攻略困難科目です。私が出会った受験生の多くが苦戦していました。
出題数が少なければ捨てることも可能です。しかし、経済学全体で以下の出題割合を占めるため、その戦略は賢明とはいえません。
| 経済学(ミクロ経済学+マクロ経済学)の出題数
・国家一般職:10問/40問 ・東京都特別区:10問/40問 ・地方上級:11問/40問 ・市役所上級・中級:11問/40問 |
そこで、本記事では、マクロ経済学に絞って、どのように学習をしていけば、8割程度の得点ができるかについて解説していきます。公務員試験は6~7割の得点で筆記試験を通過できる年が多いので、8割取れるということは、得点源科目化(≒得意科目化)していることを意味します。
なお、紹介する学習方法は、初学者で予備校に通っていない方を想定し、入手可能な書籍しか用いません。そのため、どのような方にも取り入れられます。是非、この記事を参考に勉強を進めていっていただき、マクロ経済学を得意科目化してください。
※本記事は、国家総合職を除く大卒公務員試験種を対象としています。
※ミクロ経済学については、下記の記事を参照ください。
2.マクロ経済学とは?
マクロ経済学は、一国全体の経済に関する理論を学びます。例えば、失業率が下がっているとき、物価はどうなっているかだったり、一国の経済モデルを設定し、財政政策や金融政策が効果があるのかだったりを学びます。
そして、公務員試験で出題されるマクロ経済学の主な範囲は以下の通りです。
(1)国民経済計算関連
一国の経済活動は国際比較可能な形で記述されています。これを国民経済計算というのですが、ここにある様々な指標を学びます。代表的には、GDP、物価指数などです。数値の現況は教養試験の時事などで問われ、マクロ経済学では各指標の定義を適切に理解しているかが問われます。いずれにせよ、理論というよりも統計の話の単元です。
(2)財市場分析(45度線分析)
モノやサービスの取引をする市場を財市場と言います。この市場における総需要と総供給を導出し、その均衡はどこになるのかであるとか、インフレギャップ、デフレギャップ、乗数理論、ビルト・インスタビライザーとかを学びます。
(3)貨幣市場分析
おカネに関する需要(貨幣需要)と供給(貨幣供給)に関する論点を学びます。ここでは、貨幣需要曲線と貨幣供給曲線の導出と均衡だけでなく、貨幣の定義、信用創造、中央銀行の役割(金融政策含む)などを学びます。
(4)ISーLM分析
(2)と(3)の市場の同時分析をIS-LM分析といいます。ここは、頻出中の頻出単元です。毎年どの公務員試験種でも1問以上問われることになります。
(5)国際マクロ
(2)は輸出入がないモデルを学習するのですが、これを変更します。海外とやりとりがあることを開放経済モデルと言いますが、そのようにします。それから、為替レートの決定理論や、国際収支曲線(BP曲線)を(4)に加えたISーLMーBP分析(≒マンデル・フレミングモデル)などが出題されます。
(6)AD-AS分析
(4)に労働市場を加えて同時分析することをADーAS分析と言います。三つの市場を含んだモデルにおいて財政・金融政策がどうなるかを問う単元です。
(7)ケインズ派以外のマクロ経済学
(2)~(6)は、ケインズというマクロ経済学の創始者並びにその影響を受け理論を発展させた学者群(ケインズ派と言われます)の考え方に基づいた理解です。しかし、マクロ経済学には、ケインズ以外の主流派経済学である古典派(新古典派含む)の考え方もあります。その論点を学びます。
また、ケインズ型消費関数以外の消費関数やケインズの投資理論以外の投資に関する理論も学習します。
(8)経済成長論
(2)~(5)は数か月程度、(6)(7)でも数年程度の期間を想定した理論なのに対し、経済成長論はかなり長期のマクロ経済学を分析した理論です。こちらも、ハロッド=ドーマー型というケインズ派と、ソロー=スワン型という古典派の経済成長論があります。また、ソローの成長会計という経済成長の要因分析もよく出題されます。
その他、インフレーション、フィリップス曲線などの単元もあります。なお、赤字がよく出題され、青字がそれに続き、黒字がさらにそれに続く出題のイメージとなります。
3.マクロ経済学の学習方法(参考書紹介付き)
ここからは、マクロ経済学の攻略方法をお伝えします。
(1)インプット編
まずは、公務員用に書かれた基本書での学習です。このとき、大事なことが2つあります。1つ目は、前から順番に学習をしていくということです。理由は、マクロ経済学という科目が積み重ねだからです。前の単元を引き継いで次の単元が展開されていくということです。例えば、上述「2」の(2)財市場を理解した上で、(3)貨幣市場を押さえないと、(4)のISーLM分析ができないわけです。
2つ目は、多少分からないところがあっても気にせず先に進み、後で関連したときに返り読みするということです。理由は、後になればなるほどモデルの設定が複雑になっていくのですが、そのときに以前のモデルとの比較がされますので、その時に以前の理論が分かり理解が深まるからです。
例えば、筆者が初学者だったとき、AD-AS曲線の学習する際に「ここから物価が動きます」とテキストにあったことで、「IS-LM分析って物価一定が前提だったんだ」と認識し、そこで振り返るとIS-LM分析の理解が深まりました。初学者は、筆者みたいに、最初はよく分からなかったり、重要なところだと思わずさらっと読み進めてしまったりしがちです。そして、後の記述に触れることでその点が分かってきて、理解が深まることが多い科目がマクロ経済学です。この点を含んで通読と返り読みをすると良いでしょう。
この2点を気を付けつつ、学習に使う基本書としてお勧めなのが、
『公務員試験 ゼロから合格 基本過去問題集 マクロ経済学』(以下、ゼロから本と表記します)です。
こちらの本は、テキスト部分と問題部分があります。1周目は、問題を解かなくて良いので、どんどんテキスト部分を上記の2点に気を付けながら読んでいきましょう。
(2)アウトプット編
『ゼロから本』は2周目において、テキスト部分を再読した後に問題を解いていきましょう。ここから、アウトプット編がスタートします。
3周目は各章とも、問題から解いていき、間違えた場合に、復習として解説だけでなく、テキストの該当部分に立ち返える使い方をします。これで、かなりの解答力が身についたと言えます。
ただ、『ゼロから本』は、少しひねった問題などが少ない傾向にあります。そこで、仕上げとしては、問題集を使います。
問題集は、スーパー過去問も良いですが、数学が苦手な方&見開き問題が好きな方はLECの解きまくりシリーズの方が良いでしょう。
『2025-2026年合格目標 公務員試験 本気で合格!過去問解きまくり! 【14】マクロ経済学』
なお、問題集は、『ゼロから本』で収録されていない問題だけをやればOKです。問題集も2~3回転(2,3回転目はできなかった問題のみ行う)することで、8割の解答力がつくことでしょう。
4.まとめ
本回は、マクロ経済学の択一式を試験当日に8割正答するための方策を伝えました。お勧めの参考書と利用法は、『ゼロから合格!マクロ経済学』でインプット&アウトプットした後に、スーパー過去問か解きまくりシリーズのマクロ経済学でさらなるアウトプットとなります。
そして、インプットの時には、前から順番に行うことと、多少分からない部分があっても立ち止まらず読み進めるということが大切です。先に進んで見て、前との比較部分がきたら振り返り学習をすると良いでしょう。
以上が参考になれば幸いです。
なお、こうした勉強法をしようと挑戦したとき、どうしてもインプットがうまくいかない(分からないところが多すぎてさすがに読み進められない)であったり、アウトプットしてみたけれど全然解けるようにならないであったりの場合は、個別レッスンを受けると見通しが持てたり、改善ができたりするのではと考えます。
究進塾では、個別指導で経済学指導をしていますので、興味がある方は無料相談・体験授業などをご検討ください。お待ちしています。
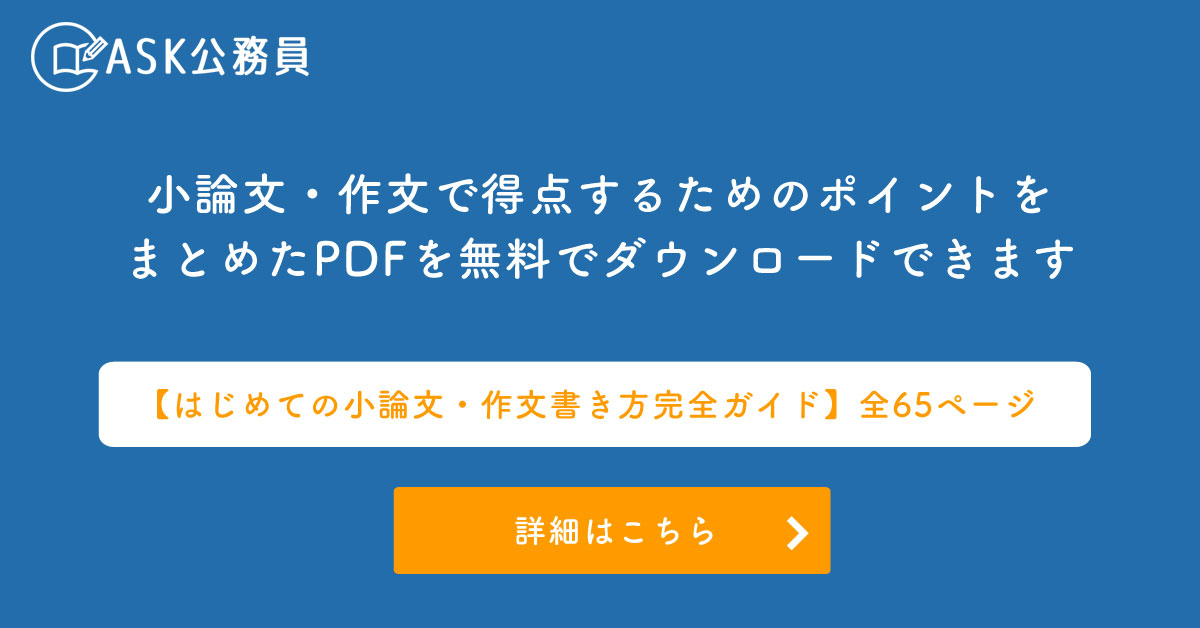

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ